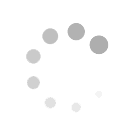「星に願いを」(1987)― 予測可能なファンタジーコメディの魅力と限界
1987年に公開された「星に願いを」(原題:Maid to Order)は、1930年代の心温まる社会コメディを思わせる作品だ。あの時代に作られた映画のように、裕福な階級から貧しい生活へ転落する物語を通じて、人生の教訓を描いている。しかも、この映画は長らく大人の映画では見られなかったギミックを導入している―妖精のゴッドマザーだ。魔法の杖を一振りして、わがままな金持ちの娘を、仕事もなく飢えたティーンエイジャーに変えてしまう。この設定は、ファンタジーと現実のブレンドとして興味深いが、果たして現代の観客にどれだけ響くのだろうか?
私は数多くの映画をレビューしてきたが、この作品は予測可能性の高さとキャスティングのミスマッチが目立つ一方で、特定のキャラクターの魅力が光るポイントもある。星2つという評価は、映画の善意ある試みを認めつつ、その実行の甘さを反映している。以下では、物語の構造、テーマ、演技、監督のスタイル、そしてこの映画が80年代の文化に与える影響について、詳細に分析していこう。できる限り長く、深く掘り下げることで、この映画の本質を明らかにしたい。
物語の中心は、ジェシー・モンゴメリー(アリー・シーディ演じる)という、典型的なわがままな金持ちの娘だ。彼女は父親のチャールズ(トム・スケリット)から甘やかされ、夜通しパーティーを楽しみ、薬物やスピード違反で逮捕されるような生活を送っている。チャールズは慈善財団の会長で、娘の将来を心配するが、ジェシーは父の善意を無視し、金をせびる嘘をつき続ける。ある夜、チャールズは苛立ちのあまり、「こんな娘がいなければよかった」とつぶやく。
この言葉を聞きつけたのが、ジェシーの妖精のゴッドマザー、ステラ(ビバリー・ダンジェロ)だ。彼女は魔法を使ってチャールズの願いを叶え、ジェシーの過去を消去してしまう。ジェシーはロサンゼルスの街路で目覚め、高価なパーティードレスを着たまま、誰も自分を認識しない世界に放り出される。家に戻っても、メイドに追い返され、父親は彼女の顔を見ても無反応。彼女は一文無しで、仕事を探さなければならない状況に追い込まれる。
やがてジェシーは、ロックンロール・プロモーターの夫婦、ジョージェット(ヴァレリー・ペリン)とオードリー(ディック・ショーン)の家でメイドとして雇われる。ここで彼女は、黒人の料理人やラテン系のメイドたちと一緒に働き、家事の厳しさを学ぶ。最初は不平不満を漏らすが、徐々に彼らの友情に触れ、自分がこれまでどれほど自己中心的だったかを悟る。物語は、ジェシーが運転手のニック(マイケル・オンキアン)と恋に落ち、父親との関係を修復する方向へ進む。最後は予想通りのハッピーエンドだが、そこに至る過程でいくつかの心温まる瞬間がある。
このプロットは、シンデレラの逆バージョンと言える。プリンセスがメイドに落ちぶれ、そこで真の価値を学ぶというストーリーは、古典的な寓話の変奏だ。しかし、80年代の設定に置くことで、消費社会や階級格差の問題を浮き彫りにしている。
「星に願いを」は、表面上は軽いファンタジーコメディだが、その奥には社会的なテーマが潜んでいる。1930年代の映画のように、富裕層の無知と貧困層の現実を対比させることで、観客に「トラックの反対側」の生活を思い起こさせる。ジェシーの転落は、単なる罰ではなく、成長の機会として描かれる。彼女は家事の大変さを知り、他者の苦労を理解するようになる。これは、80年代のレーガン時代における「自己責任」のイデオロギーを反映しているのかもしれない―金持ちの娘が自力で這い上がる姿は、アメリカンドリームの変形版だ。
また、映画は家族の絆と赦しの重要性を強調する。チャールズの願いは一時的なものだが、ステラの魔法がそれを現実化させることで、親子関係の再構築が物語の核心となる。ステラ自身も、チャールズとデートを始めるというサブプロットがあり、これはコメディの要素を加えるが、少々強引に感じる。
一方で、テーマの扱いは浅い。ジェシーの変身は魔法によるものなので、彼女の内面的な変化が本物かどうかが曖昧だ。現実の社会問題―例えば人種差別や移民の苦労―は、黒人料理人やラテン系メイドのキャラクターを通じて触れられるが、ステレオタイプ的に描かれ、深掘りされていない。映画は善意に満ちているが、予測可能な展開が多すぎて、観客を驚かせる力が弱い。たとえば、ジェシーがメイドの仕事に慣れる過程は、モンタージュシーンで簡単にまとめられ、もっと詳細に描けなかったのかと思う。
さらに、ジェンダーの観点からも興味深い。ジェシーは女性として「わがまま」から「思いやりある」存在へ変わるが、これは伝統的な女性像の押しつけではないか? ステラのゴッドマザーは、強い女性の象徴として機能するが、彼女の役割は結局、ジェシーを「正しい道」に導くだけだ。80年代のフェミニズムの波の中で、この映画は保守的なメッセージを発しているように見える。
アリー・シーディのジェシーは、映画の中心だが、ここに最大の問題がある。シーディは「ブレックファスト・クラブ」や「ショート・サーキット」で知られるように、親しみやすい魅力を持つ女優だ。しかし、わがままな金持ちの娘として、彼女の演技は説得力に欠ける。彼女の表情や仕草からは、悪意や自己中心性が感じられず、むしろ最初から好感が持てる。ジャック・ワーナーの有名な言葉を借りれば、「ビバリー・ダンジェロを金持ちのビッチに、アリー・シーディをゴッドマザーに」キャストすべきだった。シーディの自然な優しさが、キャラクターの変身を薄めてしまうのだ。
一方で、ヴァレリー・ペリンと故ディック・ショーンの夫婦は、映画のハイライトだ。彼らは「俗悪さを下回る上昇」タイプのキャラクターで、メル・ブルックスが思い浮かぶような、単純で馬鹿馬鹿しいが、互いに深く愛し合う夫婦を演じている。物質主義に溺れながらも、互いの絆が本物で、観客を笑わせる。ショーンのコミカルな演技は特に出色で、彼の存在がなければ映画はもっと平板になっていただろう。
ビバリー・ダンジェロのステラは、妖精らしい風変わりさを出しつつ、ユーモアを加えている。彼女の魔法のシーンは、80年代の特殊効果として今見ると古いが、当時は新鮮だったはずだ。トム・スケリットのチャールズは、安定した演技で父親の葛藤を表現するが、もっと深みが欲しかった。マイケル・オンキアンのニックは、恋愛相手として機能するが、印象が薄い。
全体として、脇役が主役を支えている構造だ。シーディのミスキャストが惜しいが、ペリンとショーンの化学反応は、映画を救っている。
監督のエイミー・ホルデン・ジョーンズは、「スランバー・パーティ・マサカー」などのホラーで知られるが、ここではコメディに挑戦している。彼女のスタイルは、明るく軽快で、80年代のポップカルチャーを取り入れている。ロックンロールの要素や派手なファッションは、当時のトレンドを反映し、視覚的に楽しい。音楽はジョルジュ・デルリュの作曲で、ディスコバージョンの「スピリット・イン・ザ・スカイ」やメリー・クレイトンの歌が印象的だ。
しかし、演出は予測可能すぎる。魔法のシーンは陳腐で、ジェシーの成長過程が急ぎ足。もっとユーモアのタイミングを工夫すれば、クラシックなコメディになっていたかもしれない。特殊効果は予算の限界を感じさせるが、それが逆にチャーミングだ。
公開当時、「星に願いを」は批評家から賛否両論だった。ロッテン・トマトのスコアは42%で、私の2つ星評価もその平均を反映している。ニューヨーク・タイムズのレビューでは、シーディの演技を褒めつつ、全体の浅さを指摘。観客スコアは55%で、80年代のファッションやノスタルジアを愛する人々に支持されている。
この映画は、シンデレラの逆転物語として、後年の作品に影響を与えた。例えば、「プリティ・ウーマン」や「デビル・ウェアズ・プラダ」などに似たテーマが見られる。80年代の消費文化を風刺しつつ、結局はハッピーエンドで締めくくる点は、時代の本質だ。しかし、今日見ると、人種や階級の描写がステレオタイプ的で、現代の多様性基準に合わないかもしれない。
「星に願いを」は、善意に満ちた映画だが、予測可能性とキャスティングの弱さが足を引っ張る。ペリンとショーンのような輝く瞬間はあるが、全体として記憶に残る傑作ではない。それでも、軽いエンターテインメントとして楽しめる。人生の教訓をファンタジーで包む試みは評価したいが、もっと大胆さが欲しかった。星2つ―観る価値はあるが、期待しすぎないで。
(2025年 10月 11日 13時 06分 追加)
OPPAIUNKO