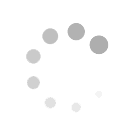注意事項
商品所在地距離海外收貨處(神奈川)較遠,請注意日本運費
google翻譯
google 翻譯僅供參考,詳細問題說明請使用商品問與答
「母の曲」――永遠の母性と現実の残響
1937年、日本映画の黎明期に生まれた山本薩夫監督の『母の曲』は、吉屋信子の同名小説を原作とした感傷的な家族ドラマである。この作品を前に、私はフランスのリアリズム映画の系譜を思い浮かべずにはいられない。ルネ・クレールやジャン・ルノワールの作品群が、日常の微細な仕草を通じて人間の内面を深く掘り下げるように、山本のカメラは日本独自の静謐な情感を、抑制された構図で捉え出している。公開当時の日本は、軍事化の影が忍び寄る時代背景の中で、こうした家庭内の微妙な亀裂を描くことで、観客に普遍的な喪失感を呼び起こした。資料として添付された三点のパンフレット――前篇の情感豊かなあらすじ抜粋、キャストのポートレイトを伴う後篇のストーリー展開、そして全体を俯瞰する宣伝文――は、この映画の核心を象徴的に示している。そこに記された「母の涙は、子のために流れる」という一節は、単なるメロドラマの修辞ではなく、視覚的なリアリティとして画面に刻まれている。
物語の骨子は、決して複雑ではない。大学教授の淳吉(岡譲司)は、20年前の家産倒産の傷跡を負い、才能あるピアニストの香苗(入江たか子)との恋を断念する。代わりに、田舎の温泉宿で働く春子(英百合子)と結婚し、娘の雪子(原節子)をもうける。春子は夫の成功を陰で支え、貧窮と孤独に耐えながら娘を育てるが、淳吉の浮気――皮肉にも香苗との再会――が離婚の引き金となる。成長した雪子は、香苗の養女として上流社会に溶け込み、生物学の道を志すが、母・春子の存在を忘却の彼方に追いやる。春子は、娘の結婚式の日に、遠くの客席から涙を堪え、静かに去る。パンフレットの前篇では、「母の曲」が象徴的に繰り返され、春子の内なる旋律として描かれる。後篇の資料では、雪子の成長と母の犠牲が対比的に語られ、「雪子の未来のために、春子は影となる」との記述が、物語の悲劇性を強調している。これらのテキストは、単なるプロモーションではなく、映画のテーマを詩的に凝縮したものであり、山本監督の脚本家・木村千依男、八住利雄との共同作業の賜物だ。
山本薩夫の演出は、1930年代の日本映画特有の静的な美学を体現している。友成達雄の撮影は、深層焦点を思わせる長回しを多用し、春子の台所での孤独な仕草や、雪子のピアノ練習の場面で、空間の奥行きを活き活きと描き出す。英百合子の演技は特に秀逸だ。彼女の表情は、過剰なメイクを排し、自然光の下で微かな皺が刻まれる。資料のポートレイト写真――看護婦姿の春子が、穏やかな微笑みを浮かべる一枚――は、彼女のリアリズム演技を予感させる。百合子は、春子の苦痛を叫びや涙ではなく、静かな視線で表現する。これは、私が『自転車泥棒』で称賛したヴィットリオ・デ・シーカの手法に通じる。母の愛は、劇的なジェスチャーではなく、日常の反復――洗濯物を干す手、娘の弁当を包む指先――を通じて現れるのだ。岡譲司の淳吉も、野心と後悔の狭間で揺れるインテリを、抑制されたボディランゲージで体現し、香苗役の入江たか子は、洗練された都会の女性として、春子の田舎臭さと対比を成す。原節子の雪子は、若々しい無垢さが光るが、後半の成長ぶりは、母の犠牲を無自覚に受け継ぐ象徴として機能する。パンフレットのキャスト紹介部――「英百合子:母の無言の強さ」「原節子:青春の純真」――は、これらの演技を的確に予見している。
この映画の力は、母性の神話化ではなく、現実の残酷さを直視する点にある。吉屋信子の原作は、女性の社会的抑圧を背景に、母の犠牲を美化しがちだが、山本はそれを相対化する。離婚後の春子は、温泉宿に戻り、再び下働きとして生きる。画面は、湯気の立ち込める浴場で彼女の疲弊した背中を捉え、伊藤昇の音楽が、ピアノのメロディではなく、和楽器の哀愁で彩る。ここに、日本映画の独自性がある。欧米のメロドラマが個人の救済を夢見るのに対し、『母の曲』は集団の倫理――家族の崩壊と再生――を問いかける。1937年の日本では、こうしたテーマは、戦前の家族国家観と微妙に乖離し、観客に内省を促しただろう。資料の第三点、全体のあらすじまとめでは、「母の曲は、永遠に響くが、子はそれを聞かぬ」と締めくくられ、観客に問いを投げかける。この言葉は、映画のエンディング――春子の去り際のシルエット――を象徴し、リアリズムの極みだ。
しかし、批評家として一抹の不満を述べねばならない。後篇の展開がやや唐突で、雪子の心理描写が浅い。原節子の演技は輝かしいが、養女としての葛藤が、もっと長回しで深掘りされていれば、物語のリアリティは増しただろう。とはいえ、これは時代的な制約――トーキー初期の技術的限界――によるものだ。全体として、『母の曲』は日本映画の黄金期への序曲であり、山本薩夫の後年の傑作群――『忠臣蔵』や『人情紙風船』――を予感させる。母の曲は、決して甘い子守唄ではなく、人生の不協和音を奏でる。今日、再びこの作品を振り返る時、私たちは自身の母性・父性を問い直すだろう。春子の涙は、画面の向こうで、なお静かに流れ続けるのだ。
(2025年 10月 3日 19時 58分 追加) HAHANOKYOKU >